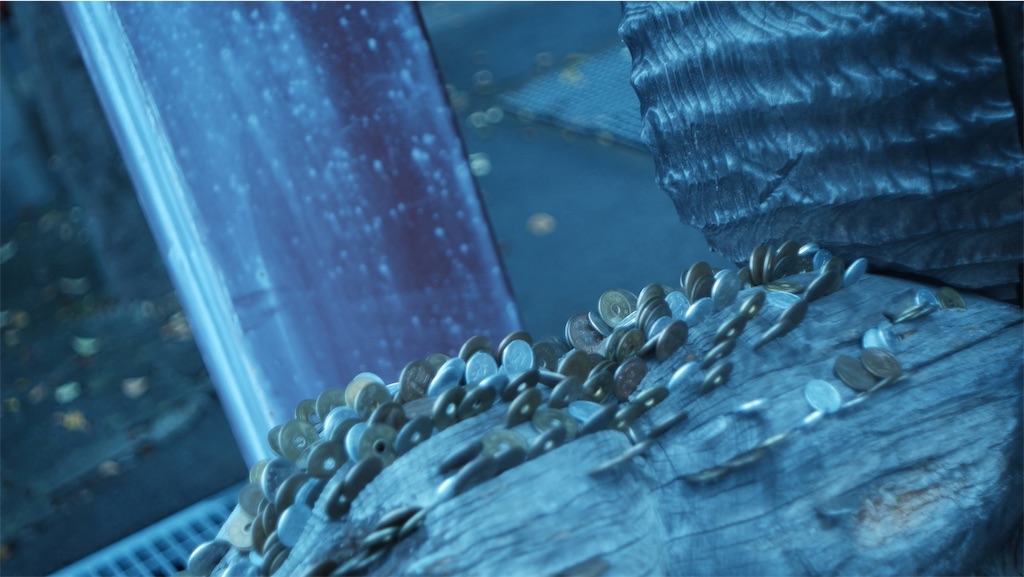ひとに自分が誕生日であることを報告するのが、わたしは苦手だ。ちょっと気恥ずかしい感じがしてしまって自分から言い出すことができない。だからといって、祝ってほしくないというわけでは決してなくて、むしろ、おめでとう的なLINEが殺到することを、心の奥底では待ち望んでいるのだ。だから、誕生日は、ちらちらと、祝ってくれないかどうか、LINEの通知を脇目に見ながら1日を過ごすことになりかねない。
こう、主役の立場に自ら躍り出ることに、若干の苦手意識があって、誕生日然り、自己紹介しかり、なかなかうまくできない。
「自分を売り込まなければ!」みたいな気持ちが強いときは、こういう自己紹介の記事だったり、お仕事募集記事だったり、書こうとするときもあるのだけれど、どうも疚しいことをしている気持ちになってきてしまって、筆が止まってしまう。このnoteの4年前の記事は、かなり雄弁に自分のことを書いているけれど、「もどき」止まりである。助成金なんかの申請書では、そういうゲームだと思って割り切れる自分もいるのだけれど、ブログやTwitterとかで、わざわざ自己紹介しようという気には、なかなかなれないでいる。
16personality診断(webの性格診断)とか、少し前に流行っていたけれど、自分の結果とか、すごく恥ずかしく感じてしまう。それに、その診断結果から溢れ出て、はみ出している、自己の過剰な部分が無かったことにされそうな感じがして、ちょっと恐ろしい感じがする。性格診断によるタイプ化にせよ、HSP等々のカテゴライズにせよ、言葉にしてしまった途端、それぞれが抱いているはずのドロドロとした部分(あるいは、バタイユ的に言えば「呪われた部分」)が、どうやら失われていくようである。
その点で、演劇や詩などを通した、自己のはみ出しをドロドロとしたまま形にするモノ化は、わたしにとっては、そんなに恥ずかしくないような感じがする。それはたぶん、演劇や詩が、整理整頓された言葉よりも、もう少し、身体の側に馴染んだ言葉の芸術だからなのだと思う。それらの分からなくてよさは、わたしたちのはみ出しを、それぞれのはみ出しのままにしておくことに繋がるだろう。
そういうわけで、2024年は、整理整頓されていない、詩の言葉での自己紹介をつくってみたいと思う。金はないけれど時間だけはあるのだから、そういう無駄な時間を大切にしていきたい。役に立つことは、それ自体でなんの役にも立たないが、無駄であることは役に立つでも立たないでもないのだから、無駄であることは、そんなことにびくともしない。わたしも、無駄であることに倣って、どこ吹く風でやっていきたい次第である。