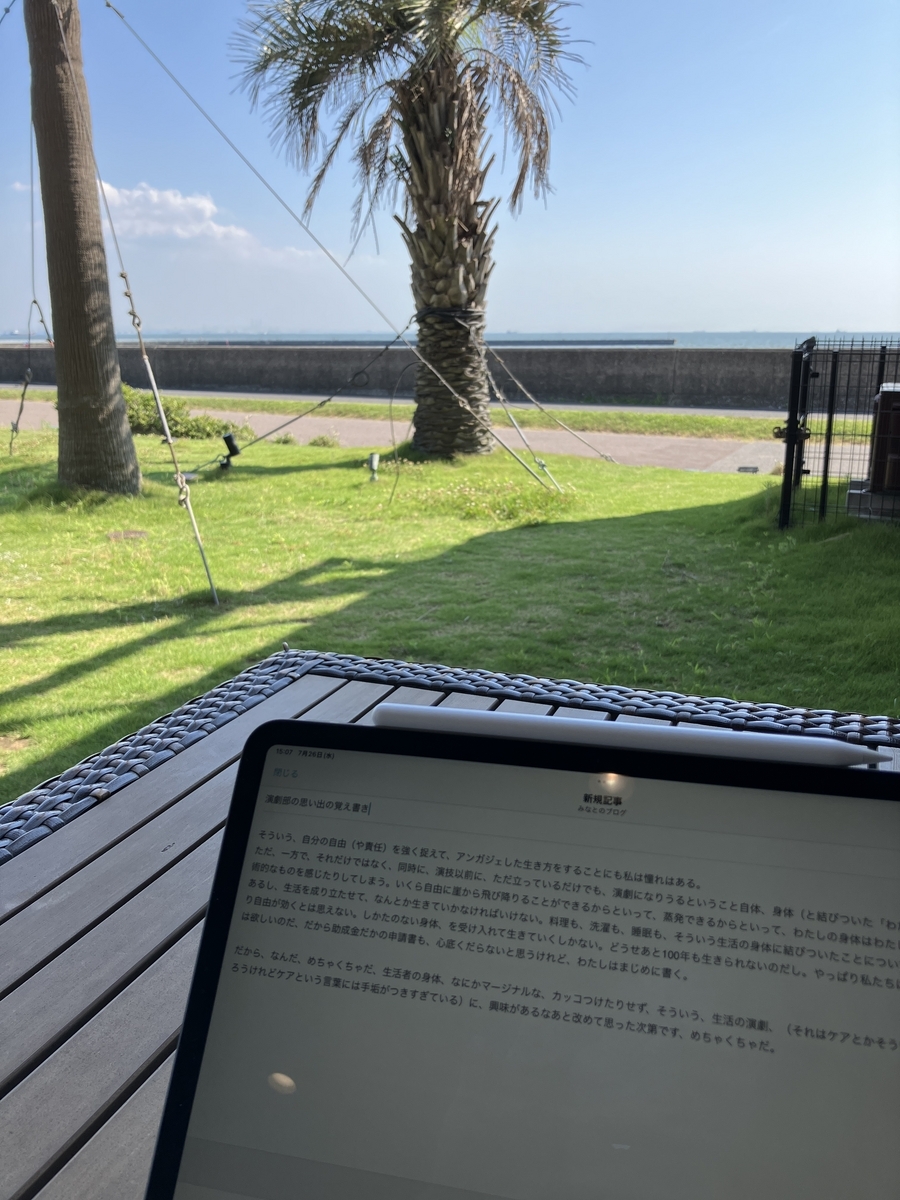今日は、わたしが作品作りに関わらせていただくときの、関わり方について、ある程度文章にしておきたいと思います。
というのは、以前わたしが所属していた劇団の主宰の方が、最近のnoteで「鈴木(私)が、公演のプロデューサーとして、とにかく新しい演劇を作って注目を集めようと言っていた(がゆえに、主宰が演出家を務めていた作品がつまらなくなってしまった)」という主旨のことを(名指しではないにせよ)書いていたらしく、そのことを、わたしの信頼できる友人が不審に思って、わたしに教えてくれました。
わたしは、(これを事実だとはとても思えないのだけれど)こういう正確性の乏しいネットの記事に対して、逐次、反論することは基本的にはありません。他にやっておきたいことも多いし、反論していると悲しくなってくるし・・、いくら酷いことを書かれても、「泣き寝入り」して終わらせることがほとんどです。
だけれど、最近はryuchellさんの自殺のことなどあり、少し考え方が変わりつつあります。わたしが「泣き寝入り」することによって、今後、ほかの方が攻撃されるということもありうるかと思うからです。それは、その主宰の方が、ではなくて、社会全体のなかでそういうムードが作り上げられる、ということです。(「どうせ誰も反論してこないからいいだろう」というような空気が広がっていく。)
じゃあ、どうしよう。
そこで、今日は、ちょっと少し視点を変えて、これを、私の考え方について書くための、よい機会として捉えてみたいと思います。舞台芸術 の創作に関わるときの「やり方(ポリシー)」について、書いてみたいと思います。
ふだん、こういうことを考えながら、舞台の作品制作に関わっています。
-------
1.制作者やプロデューサーとして参加した作品においては、作品の内容について口を出すことは、原則ありません。
制作者として参加するときは、作品の内容に口を出すことは、先方から求められない限りは、ありません。三権分立 」の考え方に限りなく近いものを想定しています。「俳優」「制作者」「演出家」の責任の範囲は、明確に分けた方がよいのではないかと考えています。)
ただし、口を出さないとはいっても、明らかに倫理的に問題がある(たとえば、差別的な表現がある)ときには、それが作品にとって本当に必要なのかどうか、必ず、尋ねるようにします(その場合でも、中身に対して、検閲のようなことをすることは、これまでも、これからも、ありません。)
2.ドラマトゥルクとして参加した作品においては、一切の忖度なく、作品について口を出します。そのために、(今のところは)すべて無償で引き受けています。
ドラマトゥルクは、基本的には、座組の一員として、演出家をサポートする立場だと考えています。他方で、(マイルドな表現にはしつつも)問題があると感じたときには、それについて、できる限り説得的な形で、指摘します。
というのは、わたしが参加させてもらう作品はすべて、何らかの社会問題を扱った作品で、その(何らかの形での)当事者が観劇に来る場合が非常に多いです。社会学 者としての何らかの知識を期待されて声をかけていただくことが多い以上、作品に何かしらの問題(事実上の問題・倫理的な問題など)がある場合は、口を出します。
このとき、金銭を媒介とした忖度が生じないよう、劇団や演出家側から、私は一切の報酬を頂戴しません(これまでも何度かドラマトゥルクとして作品に参加させてもらったことがありましたが、すべて、無償でやっています)。
3.アート市場で注目を浴びるためだけに作られた作品には、今後も、一切、関与しません。
たびたび、以前書いていたnoteやブログで取り上げていたテーマ(たとえば、この記事 など)ですが、「珍奇な試みをすることで、アート市場で注目を浴びる」というだけの作品には、今後も、一切関与しません。(これまでもそういう作品に関与したつもりは、私の方ではありません)
また、「流行り」とされている社会問題(とくに「マイノリティ」と名指される当事者がいる問題)を、ろくに勉強もしないまま、不十分な形で取り扱っている作品に対しても、一切関与しません。
なにか新しいことを説得的にするためには、必ず、それを理解してもらうための言葉が必要です。そして、そういう言葉は、作り手が、まことの意味で勉強をし、研鑽を重ねたときにしか、出てこないように私は思います。勉強不足でその題材を取り扱うことは、ときとして、差別を助長することにもつながります。
4.座組内での差別・排除があったときには、できる限り、言葉にします。改善がされなかったときには、降板を申し出ます。
差別的だと感じられる振る舞いが、放置されている劇団や座組に、わたしが居続けることはありません。
ハラスメントのガイドライン に違反しているかどうか、というような話以前に、そもそも、何を、その座組では差別だと考えるのか、というところから、私は話し合いたいです。それでも問題があると感じられたときには、わたしは、なるべく迷惑のかからない形で、団体を去ります。
5.自分が作者・演出家として関わった作品について、作品の質を、俳優やスタッフに帰責させることはありません。
最近は、作り手として関わらせてもらう機会が、ありがたいことに何度かあり、今後も、少しずつ増えていくのではないかと予想しています。そうしたなかで、舞台芸術 はいろいろな人が関わる生き物のような部分があって、作家や演出家だけで制御しきれない部分も多いと思いので、今後、創作の過程で、自分の責任の範囲が曖昧になりかけることも、もしかしたらあるのかもしれません。
-------
以上は、ふだん考えていることの一部で、すべてを網羅しているわけではありません。
川の流れが段々と変わっていくように、考え方も、人も、変わっていきます。ここに書いたことも、時間をかけて、少しずつ、私のなかで変わっていくのだと思います。
minatosuzuki.openaddress@gmail.com
もし、どなたでも、なにかご意見あれば、メールでも、なんでも、連絡ください。なにか一緒に食べながら、みたいなのでも、もちろん大丈夫です。
海も川も、夏になると色が違う気がする