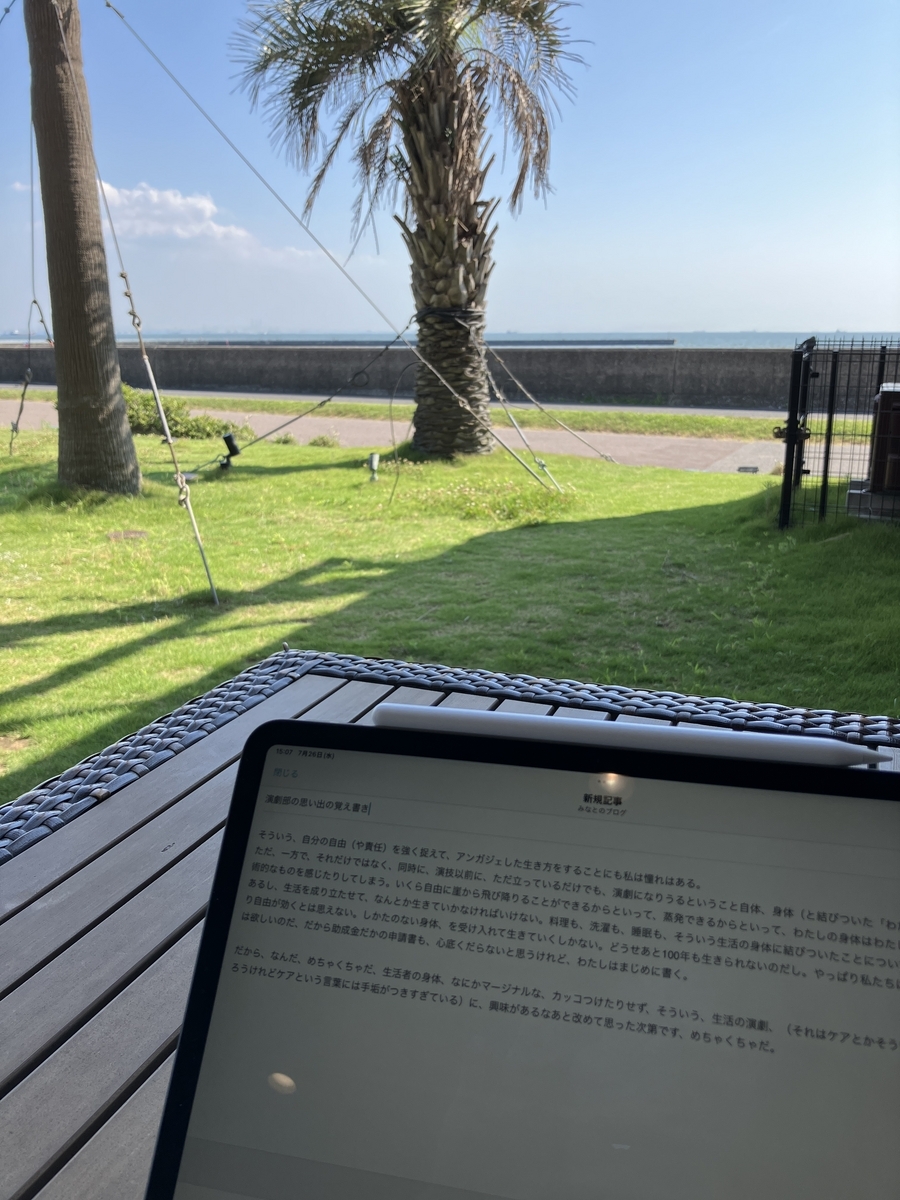人生最後の夏休みがはじまった。博士号が取れたのはいいものの、生活は、ちっとも豊かにはならないし、勉強したいことも、しないといけないことも尽きないので、押し潰されそうになったりもする。生活をすることと、研究をすることの両立は、この国では、とても難しい。
だから、今日は海にきた。(家の近所に海がある)
海を見ている間くらいは、ひと息ぐらいついてもバチが当たらないような気がする。
家にいると、生活の不安や研究への強迫観念など、頭に浮かんできてしまって、いけない。
昨日、たまたま高校の演劇部の恩師とバッタリ会ったのだった。
たぶん、わたしは(見た目はわりと変わっているのだが)生活のスタイルはあまり変わっていないように思う。昼に好きなことを勉強して、夜に演劇など作ったりしている。こういう生活をギリギリであれ、続けることができているというのは、さいわいなことだ。
恩師は、いまも夏休みになると、演劇部の高校生や先生たちと一緒に、ちいさな演劇を集めた「小芝居まつり」を上演しつづけているらしい。(先生たちも、3日だけ練習して、出演したりするらしい。)それってすごいことだと、大人になった今の私は思う。
演劇は、上手な俳優が出ているからといって面白いとは限らないところが、いいところだ。なにも喋らずに、ただ立っているだけの人が居てもいいし、歌っている人も踊っている人もいてもいい。(いや、いてもいい、というか、とにかく、いるのだ。)
シェイクスピアという劇作家は、「人生みなこれ一つの舞台」と登場人物に言わせたりしていたようだ。
人生が日頃から舞台なのだとしたら、わたしたちは、芸術としての舞台で、わざわざ演じ直す必要もないのかもしれない。普段から、演技しているということになるのだから。(わたしは、あんまりそうは思っていないけれど)
ただ、それでも、あえて、人生のなかで、演劇という一つの舞台を芸術として作ることの良さは、日々の人生という舞台を、その時間だけでも中断させてくれることにあるのかもしれないな、と思う。演劇は、人生の舞台のなかに、入れ子として、ありえたはずの(そして決してありえなかった)舞台を作り出す。演劇は、日々の生活から閉ざされているがゆえに、ありえたであろう日々の生活に開かれている。
昨日は、わたしのありえたはずの人生の可能性を、一瞬だけ、垣間見た気がしたのだった(が、見てもしょうがないので忘れることにした)。
演劇(やほかの芸術)がときどき見せてくれる、ありえたはずの生の可能性を、現実の人生の自由を再確認するための契機として捉えることもできるのかもしれない。実りある植物を育てるときに、小さな芽を間引いていくように、ありえた可能性を諦めて、可能性のなかから自由に自分を剪定し、自分なりの「役」を作り続けるのが人生なのだから、そういう意味で、わたしたちは、いつでも自由に晒されているのだ、というように。(急に崖から飛び降りるように、誰しも、明日には、いまの人生の舞台から降りて、異なる役を演じ始めるかもしれない)
そういう、自分の自由(や責任)を強く捉えて、アンガジェした生き方をすることにも私は憧れはある。
ただ、一方で、それだけではなく、同時に、演技以前に、ただ立っているだけでも、演劇になりうるということ自体、身体(と結びついた「わたし」たち)の魔術的なものを、わたしは感じてしまう。いくら自由に崖から飛び降りることができるからといって、いまの役を辞めて蒸発できるからといって、わたしの身体はわたしの身体のままであるし、生活を成り立たせて、なんとか生きていかなければいけない。料理も、洗濯も、睡眠も、そういう生活の身体に結びついたことについて、わたしはあまり自由が効くとは思えない。この、しかたのない身体、を受け入れて生きていくしかない。どうせあと100年も生きられないのだし。
それでもって、やっぱり私たちは、ある程度お金は欲しいのだ、生きていくために。助成金だかの申請書も、心底くだらないと思うけれど、わたしはまじめに馬鹿馬鹿しく書く。
生活はくるしいけども、なんとか、やれる範囲で、生きていきたい。
だから、(いやだからってなんだ)、生活者の身体、なにか、マージナルな、いや、カッコつけたりしない、と筆を止める、とにかく、そういう、生活の演劇、(それはケアとかそういうのも含むのだろうけれどケアという言葉には手垢がつきすぎている)に、興味があるなあと改めて思った次第です、めちゃくちゃである。